只今、縦書きでレンダリング中です。フォントなどダウンロードしています...
※ライン
キッド←キラーの短い文章。
キラーが悩みをこじらせている話。報告がてら軽く肩口をはたいてやると、いつもの悪態がいつもの調子で返ってきた。続いて分厚いコートの袖先がわずかに指先をかすめた。
遠ざかる足音に、悪態と同じ口で、同じ調子で余計な一言が重なる。「流石だなキラー、愛してるぜ!」
「それは光栄だ」あとずさりするたび、足下にラインを引く。
これ以上出過ぎてはいけない。期待してはいけない。勘違いしてはいけない。
ごく浅い切り傷のように、キッドと己の間に平行線を刻む。うっすらとささくれた無数の傷口を幻視するたび、火照った心にも瞬く間に静寂が訪れるのだった。
人を恋う時につきまとう温度は、キラーの心臓に常に火傷を負わせた。無闇に上昇し続ける熱はひどい痛みを伴った。
荒れ狂う戦地に上がる火の手など目立ちもしないが、平穏な町に放たれる炎がどんなに人を絶望へ追い込むかキラーは知っている。全く熱を持たなかった頃に戻りたいとすら思った。はたしてそんな時期が本当にあったのか、今では思い出せもしない。
皮肉にも熱さを忘れていられる時が幸せだった。例えば戦いのさなか次の一手に思いを巡らす時であるとか、凄絶な死闘を演じる時だ。別種の高揚を得られる瞬間だ。
それらはこの海賊団に身を置いていれば日常の現象であった。そのためキラーは熱源を鎮めるために絶えず熱源を求め続けるという矛盾を抱えていた。しばしば仲間や敵に冷静な男だとか非情だとか温度のない生き物のように評されるのは、この熱が外に洩れていない証だと安堵した。それは感情の大部分を冷ややかに覆い隠す仮面のおかげかもしれなかった。
仮面の内は、坩堝だった。気を抜けば情欲以外のものも諸共に融けてしまいそうだった。かくも煮え滾っているのは己だけかと思うと無性に情けなくなった。しかし、あの男が自分のことを嫌っているわけはない。それは自惚れではなく断言できた。
また一本戒めを引く。
信頼を別の感情にすり替えてはいけない。
背中を預け預けられることの幸いさは、己を責め苛む激痛に代えても享受したいものだった。
けれども背中合わせでは相手の顔など見えはしない。そして覗き込むまでもなく、男は前だけを向いている。
嫌いではないのと憎からず思っているのとでは意味が違うことは、数限りなく横切る線が物語っている。
その二つの間にあるのは、底の見えない裂け目だ。埋められはしない。同じ地平に立っていても、姿が見えても、声が聞こえても、隣にいることができても、
「キラー、島が見えたぞ!」
声に振り向くと、水平線上にわずかなふくらみが確認できた。
それは、真新しい傷から滲む血の玉のようだった。
船はじきにあの島へと辿りつくだろう。にわかに心臓が波打った。
無限に重なる平行線は、時折道のようにも見える。望む場所へ続いているようにも思える。
いつかこの赤黒い傷口を踏みしめて、ラインの彼方にたたずむ男の手を掴む。
いつか、はいつ訪れるだろうか。
それはきっと今日のような風の強い日だ。
視線の先で、灯火が揺れた。※
以下蛇足。
いつも何度でも繰り返しますが、私はキッドのことを好きすぎるキラーが好きすぎる。
ラブだろうがライクだろうが基本はそこだよ。原作で実は憎んでたとか利用してましたとかいう展開が来ない限りは、キラーはキッドに魂預けてるのが前提だよ。
しかし私の中では、キッドがワンピースを手に入れられないのと同じようにキラーの想いが叶わないのが規定路線になってる。既に関係築いてるだけに拒絶された時失うものが大きすぎるので、そんな博打に出られるかって話ですよ。そのまま触れないでおけば死なない限り隣にいられるんだから。でもどうにかしたくてもがいてるキラーがすき。
このブログの女性向けカテゴリ大体もだもだしてるキラーばっかりで段々かわいそうになってくるので、いっそ「好きだ!」「おれも!」〜Happy End〜ってやりたい気もする。
1回だけ普通にイチャついてるの書いてそれはすごく楽しかったんだけど、心のどこかで「こいつらいったいどうやってくっついた……?」という疑問がぬぐえなかった。過程がとばされてるよキングクリムゾンの仕業か。
これキッド→キラーだったら丸くおさまるんじゃないかという気がするよね。問題は船長としての外面を保てるかどうかくらいで。キッドは自分の感情の赴くままリスク度外視で行動できると思うので、アクセル踏み込んでしまえ。
今度そういうのもかいてみよう。
とか言ってこいつはまたうだうだ悩むキラーをかくに違いない。
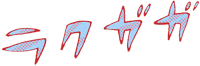





 エビコ
エビコ 2013年7月19日
2013年7月19日 :
: 