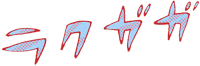只今、縦書きでレンダリング中です。フォントなどダウンロードしています...
残照 その日は、キッド海賊団にとって記念すべき勝利を飾った日であった。億越えをふたり抱えるキッド海賊団にとって、勝利は当然のことだったが、相手も名だたる賞金首であった時の勝利はまた格別のものがある。
何かにつけ思い切りのいい行動を好むキッドは、港町の宿場を全て貸し切って、盛大な酒宴を催した。
「野郎共!今夜はお前らの度を超えた暴れっぷりを賛美する宴を開く。世の中の上品ぶった奴らは眉をひそめるだろうが、このおれが全て許してやる!流した血の分まで食べ尽くせ!飲み尽くせ!」町を揺るがすような歓声と共に始まった宴は、殊の外の盛り上がりを見せた。普段は仮面のこともあり人前で酒を飲まないキラーも、早速できあがった仲間にストローとジョッキを手渡され、久々の酒を口にした。それを見たキッドはガキかよ、と笑ったが、おれもやる、とストローで飲みだした。船員達も、おれもおれもと次々に真似しはじめ、宿場は哄笑に包まれた。
皆大いに飲み、大いに食らった。キラーも珍しくあちこち仲間のテーブルを回り、饒舌に喋る。ひどく楽しい酒だった。
そして宴もたけなわという頃だった。樫の丸テーブルやリタイアして転がっている船員の間をすり抜けて、新しい酒瓶を取りに行こうとしたキラーの耳に、下っ端連中の会話が引っ掛かった。
「本当にうちのお頭は強いなあ」
「幹部連中の強さも大概すげぇぜ。キラーさんの動きを見たか?」
「ああ…あの人は化け物じみたものがあるよな……おれさ、実を言うとちょっとキラーさん怖いんだ」(……)
「そうだな。不気味、っつーか得体が知れない感じだよな」
「本当に仮面の下は人間なのかねえ」船員達はキラー本人が聞いていたことには気づかなかったようで、すぐに他愛のない話題へと興味を移す。
「夜風にあたってくる」
ふてぶてしくもカウンターの上に座し、新たな酒を空けているキッドにそう告げる。
「迷子になるなよ!」
「努力する」キッドの常ならぬ軽口も、勝利の余韻に酔っているからだろう。浮かない気分が伝わらないよう応答する。何もキッドまで醒めさせることはない。
宿場のドアを開けると、穏やかな夜風が吹いており、少々気分が和らいだ。
(化け物か…)
敵から言われるそれは一種の賛辞だが、味方から言われると、少々堪える。自らを省みるに、それも詮無いことだと思う。羨望の的にもなりうる戦闘力も、一線を越えると押し並べて脅威の対象でしかない。仮面という異形も、特に新入りからは恐れられていることを知っている。割り切るしかない、という諦観もとうの昔に身につけた。一味の中でNO.2に位置する以上、何らかの畏れは抱かれるものだ。馴れ合いで海賊団が成り立っているわけではないのだから。
(どうも酒が入るとよくない)
小さくかぶりを振る。気晴らしに散策でもしてから帰ろうと、港の方へ足を向けた時だった。路地の暗がりに人影らしきものが動くのが見えた。目を凝らしてみると、人影は半年ほど前に入団した新入りだということが分かった。
盛り場から離れた場所で、一人で何をしているのか。疑問に思い、更に近づく。口元がせわしなく動いている。手元を見ると、携帯用の小電伝虫を持っていた。ここにきてキラーは、不穏な雰囲気を感じ取った。一味には、個人で小電伝虫を持っている船員などいなかったはずだ。気配を絶ち、話の内容に聞き耳を立てる。
「……そして格納庫に迫撃砲が4台と中型魚雷が20ばかり…大丈夫です、この電伝虫だけです……」
恋人に掛ける電話にしては、色気の無い内容だ。疑惑は、ほとんど確信に変わっていた。
「ええ、潜り込むのは簡単でした。中から崩すのにそれほど時間は掛からないでしょう」
その言葉が契機だった。腰から提げた得物が閃く。
「何を話していた」
首を掻き切ろうかという迅速さで、頚部に刃を押し当てる。男が手にしていた電伝虫は地面に落ちた。同時に両の手首を捻りあげると、男はぐう、と呻いた。
「言え。返答次第では、今すぐキッドの足元に転がしてやる」
「い、痛い……」上機嫌のキッドにこんな話を持ち込みたくはないが、急を要する事態だ。なおも男は逃れようと身じろいだ。
「動くな!」
思いがけない力で、男はもがいた。キラーは反射的に男の体を強く押さえ付ける。
それがいけなかった。その行為が帰結するところは、刃先から伝わる不快な感触で理解した。しまったと思う間もなく、あっという間にほとばしった血が辺りを黒々と染める。キラーはしばし呆然とした。殺人は慣れている。しかし今足元に崩れ落ちているものは、不穏な行動をしていたとはいえ、同じ船に乗っていた仲間だ。それはキラーにとって過去形の話ではあるが、他の船員にとってはそうではない。すぐに殺すつもりなど毛頭無かった。船員達の前へ引きずり出して、本人の口から罪状を吐き出させなければ意味がないのだ。もしこの場を誰かに見られたら、釈明のしようが無い。
それでも、いくつもの死線をくぐり抜けてきた経験が、麻痺した頭を切り替えさせた。(電伝虫にログが……)
急いで転がった電伝虫を拾おうとすると、それは触れるか触れないかのところで、小さな爆発音と共に内部から破裂した。唯一キラーの正しさを証明する物が、灰燼に帰してしまった。
「あっ、キラーさん」
最悪のタイミングだ。ほろ酔い加減の足取りで、仲間が近づいてくる。咄嗟に死体を隠そうとしたが、男は気安い態度でつい、と覗き込んできた。もうキラーは為す術無く立ちすくむしかなかった。
「こんなとこ、に……え?うわ、うわあああ!!」
仲間の悲鳴を聞き付け、宿場から何人も船員が飛び出してくる。そして皆一様に言葉を失った。
グラスを手にしたまま出てきたヒートは惨状を見るや、青くなって宿場に取って返した。数瞬の後、宿場から溢れていた喧噪が消え去った。ゆっくりと、赤い男が近づいてくる。外で騒いでいた仲間も、その影を認めると、静まりかえった。キッドはおもむろに死体の側まで歩み寄ると、一瞥だけして顔を上げる。おぞましいほど赤く光る瞳が、真っ直ぐにキラーを射抜いた。
「お前がやったのか」
こいつは内通者だ、と言いかけて踏み留まる。直前に盗み聞いた会話から察するに、死体を改めたところで、確たる証拠などもう存在しないのだろう。一切の痕跡を残さない敵の小賢しさに虫唾が走る。
あるいは証拠など無くとも、キッドはキラーの言い分を信用するかもしれない。悪名高い3億の首の名を気安く呼べるのは、キラーだけだ。過失だと言えば、裏切り者を始末したのだと言えば、事情を汲んでくれる。そのくらい長い間、共に海を渡ってきた。だが、”キャプテン”キッドの名においてはその限りではないことを、誰よりも理解しているのもまたキラーだった。
「キラー、何とか言え」
どこか機械的な抑えた声色に、うっすら逼迫が滲んでいた。船員達が固唾を飲んで、ふたりの動向を窺っている。
キラーも、ひそやかに周囲の視線を窺う。驚きを隠しきれないといった者、死体に憐れみの目を向ける者、状況を把握できていない者。中でも、怯えた瞳でキラーを見つめる者が、目についてしょうがなかった。(お前達には、おれが化け物に見えるんだろう)
靴底ににじられた灰が、じり、と音を立てる。
「おれはこの船を降りる」
「……何だと?」
あまりに思いがけない台詞だったのか、キッドは一瞬表情を無くした。その横を擦り抜けるように、キラーは歩みを進める。側に居た仲間は、おののいたように後ずさった。その様に、誰にも見えない自嘲の笑みが洩れる。
「仲間殺しは、許されることじゃない。……今まで世話になった」
それが、自らの出した答えだった。
「待て」
踏み出した足が地面に縫い付けられる。振り返りはしない。だが、背中に鋭い怒りが突き刺さっているのがわかった。
「言い訳しろってんじゃねえ。だが、言わねえとわからないこともあんだろ」
「……特に何もない」一層、怒気が強まるのを感じた。後悔が無いと言えば嘘になる。キッドの怒りの矛先が、キラーが犯した行為にのみ向いているわけではないと分かっているからこそ、尚更悔いは積もる。今とて、何もかも隠さず叫んでしまいたかった。
「ああ、そうかよ」
一拍置いて、キッドは吐き捨てるように呟いた。
「お前とは長い付き合いだ。追っ手をよこすことはしねえ。今すぐ失せろ」
「頭……!」どよめきが巻き起こった。様々な感情が錯綜していて、混乱していない者がいなかった。再び一味に背を向けて歩き出したキラーを、引き留めようとする者もいたが、その手はついぞキラーの袖を掴むには至らなかった。それだけキッドの怒気は、夜を覆い尽くしていたからだ。
(これでいい。”キャプテン”キッドの決断に、間違いは無い)
キラーは、そのまま一度も振り返ることなく、闇に紛れていった。
その夜、町中から買い占めた酒樽や、食べかけの鮮やかな料理、宴の残滓は、残らずキッドの手によって破壊された。
…
キッド海賊団が港町を出航して、何日も経った。
あの一件以来、キッド海賊団の中でキラーの名前を口にすることは、半ばタブーと化していた。話題に出さないように、考えないように。日に日にその存在は、船員達が被せていく無言で覆い隠されていった。
キッドもキラーの離脱直後に荒れて以降は、普段通り采配を振るっている。しかし、内心鬱々としていることは誰の目にも明らかだった。苛立ちも悲しみも見せない代わりに、心が振れることもない。
いくら存在を覆い隠していっても、逆にその不在は存在感を増すのみだった。ヒートは、あの日のことを反芻しては煩悶していた。暗闇に佇むキラーの、諦めたような態度は何だったのだろう。海賊団が旗揚げして間もない頃からの仲間だ。血塗れのキラーの足下に仲間の死体があったとて、事情も聞かずにキラーを咎めたりしないことは本人も解っているだろうに。キラーも死んだ仲間も多少なり酔っていただろうから、酔い任せの口論が発展した過失ということも推量できる。あの男は冷静なようでいて、沸点は低い。もし仮面に関することであれば、尚更だ。
しかし、今更何を考えたところで確かめる術がないのだから、所詮推測の域を出ない。空を振り仰ぐと素晴らしい快晴が広がっており、どうせなら土砂降りにでもなればいいのに、とヒートは心の中で悪態をついた。
キラーがろくに事情も言わず出ていってしまったこと。キッドがそれを呆気なく許してしまったこと。今までの航海に比べたら何もかもが一瞬のことで、未だに信じられなかった。しばらく空を見上げていたヒートは、靄を振り払うように首を振った。船長室のドアをノックすると、一拍置いて間延びした返事が返ってきた。
「頭、その……キラーのことだが……」
キッドは瞼を閉じて、黒い毛皮をあしらった大きなソファの上に寝転んでいた。勝手に喋れという雰囲気だったので、ヒートはすぐに本題に入った。
「キラーの奴、そりゃ敵には容赦ないが、訳もなく仲間を殺したりしない。だからこの前のことにしたって、絶対に理由があったはずだ」
「……」キッドは相槌を打つことなく、話を聞いていた。
「おれにはわからない。あいつ何も言わなかったけど、あんな簡単に行かせることなかったじゃねェか。おれが報告しに行った時だって、最初は頭、キラーがそんなことするはずないって言っただろ。おれもそう思った。だから頭はぶん殴ってでも引き留めるだろうし、キラーだって理由を話してくれると、そう思ってた。なのに全てが簡単に終わりすぎて、おれには訳がわからない……!」
一気に言いたいことを全て訴える。最後はもうほとんど叫んでいた。ここ数日の鬱屈した感情を全て解き放ち、ヒートは肩で息をした。それ以上部下から言葉が出てこないのを確認し、キッドはうっすら目を開き、低い声で呟いた。
「どんな無法者でも、犯さざるべき不文律がある」
そして、億劫そうに上体を持ち上げ、背もたれに寄り掛かる。その鋭い眼でまともに見られると、自然と緊張する。
「仲間殺しだ。仲間を殺すような奴は許されない。あいつ自身もよくわかってることだ。例え理由があろうが無かろうが、殺したことじゃねえ、規律を破ったこと自体が最も罪深い」
「そしておれは、この船を率いる船長だ」
そこで初めて、キッドの辛さが生々しく感じられた。船長である以上、キッドは海賊団における絶対の存在でなければならない。枠からはみ出したものは公正に罰する。処罰の対象が、海賊団という括りを超えた無二の親友であったとしても、何一つ例外は認められない。
「……だが、クルーだって、そんな結果を望んだわけじゃない」
精一杯、振り絞るようにヒートは言葉を紡いだ。キッドもキラーも、海賊の掟に則って、苦渋の決断を迫られた。しかしそれは、決してキッド海賊団の総意ではない。そう言いたかったが、胸が締め付けられてうまく言葉にならなかった。やり場のない感情が込み上げてきて、顔も上げられない。
「風が出てきたな」
キッドはやにわ立ち上がると、ドアに向かって歩き出した。そしてヒートとすれ違う瞬間、独り言のように呟いた。
「もし今後あいつに出くわすことがあったらよ」
キッドはドアノブに手を掛けた。扉の隙間から、細く光が射し込む。
「その時はボロボロに負かしてからとっ捕まえて、死ぬまでこの船で働かせてやる」
ヒートは顔を上げた。言い方は荒っぽい。だが、そこに流れる感情は、決して冷たいものではなかった。ユースタス・”キャプテン”・キッドとはそんな男だ。
「……頭、おれもあいつに会ったら火ぃ吹きかけてやろうと思う」
久しぶりに、キッドが笑うのを聞いた。
…
左頬を、鮮烈な感覚が襲った。反射的に腕を左方向に薙ぎ払うと、情けない断末魔が上がる。痛みはすぐに怒りへと擦り代わり、キッドは吠えた。
最近かすり傷が増えた、と思う。
迫り来る敵を前に、頬を生暖かく伝うものを拭いもせず、猛々しく両腕を振るう。以前は、斬撃が迫ろうが、銃弾が降り注ごうが、それらは全てキッドに届く前に切り捨てられていた。今とて致命傷を負うことさえ無いものの、死角からの攻撃を咄嗟に防ぎ損ねることが多くなった。この小さな痛み達は、キッドを苛立たせた。その頻度は、あの男がいなくなってから数えた日々と比例していた。
最後の一人を容赦無く叩き潰すと、やっと一心地つく。尚も用心深く周囲を伺い、やがて完全なる殲滅を確信すると、船員に勝利を告げる。しかし、そこであがるのは、勝利の歓声ではない。
「痛ェよう」
「もう医務室におさまりきらねェぞ!!」
「軽傷者は床に寝かせろ!」
「キッドの頭!ヤニとラーズが……!」キッド海賊団は、明らかに変調をきたしていた。迎え撃った敵船に勝利するのは今まで通りだ。だが蓋を開けてみれば、死傷者のなんと増えたことだろうか。NO.2が離脱した、という噂が広まり、今が好機とばかりに襲ってくる賞金稼ぎが後を絶たない。話にならないような相手ばかりでも、連戦となると、船員の疲労も色濃くなる。
休む間もなく、マストの上から聞きたくもない伝令が降ってくる。
「十時の方向に敵船を発見!今の戦いに乗じて接近していた模様!」
「蹴散らせェ!」流石にキッドも焦躁感を隠しきれなくなってきた。砲弾の音も、敵味方入り交じった怒号も、戦場の全てが神経を逆撫でした。仲間を危険に晒してしまっている不甲斐なさが、自責の念と共に、激しい苛立ちへと塗り潰されていく。
戦いは、嫌が応でも思い出させる。血と破壊の中に生きていた者を。敵船から、次々と縄梯子が掛けられる。仲間達は銃を始めとした飛び道具で応戦しているが、敵は人海戦術を駆使し、次々と乗りこんでくる。キッドは舌打ちした。仲間はもう大部分が消耗しきっている。被害を抑えるためには、わずらわしい雑魚を掃討する必要がある。
「キ……」
続く言葉は、出てこなかった。口をついた言葉を掻き消すように、キッドは再び腕に磁力を集中させる。膨れ上がる怒りと対応するように、禍々しいほど巨大な武器の塊が組み上がった。その悪魔のような覇気を引き連れ、キッドは敵船のデッキへ飛び降りた。
後ろ姿は見送ってしまった。振り向いても、誰もいない。
戦いは混戦の様相を呈してきた。戦力はおおよそ拮抗している。その中でキッドの存在は飛び抜けていた。時間が経つにつれ、キッドの屠った屍が積み上がっていく。
(あの馬鹿野郎……!!)
八つ当たりと言われても仕方のないほど、情け容赦のない力がふるわれた。仲間ですら、その鬼気迫る姿に息を飲んだ。手に見立てられた大ぶりの剣が、多くの敵を刺し貫いた。半死半生の者も、残らず息の根を止める。腕に引っ掛かったままの死体は、そのまま敵に叩きつけられた。
恐怖に駆られて逃げようとした戦闘員の首を飛ばしたところで、敵船内部から仲間の怒鳴り声が響いてきた。
「頭ァ!奴ら投降してきましたぜ!船長の首を差し出すから、見逃してくれって……」
その声と同時に、敵船のクルー達はぴたりと動きを止めた。キッドも凶器を下ろし、敵船に注目する。しばらくして、仲間達が大きな布袋を抱えて出てきた。そしてキッドの目の前まで来ると、その足元に袋を投げ出した。
「……どうします?」
袋を靴先で小突くと、中身が小さく動くのが分かった。敵船の船員達は、卑屈な表情でキッドの行動を見守っている。自分だけは助かりたいという望みが、ありありと伝わってくる。そのへつらうような様子は、キッドの怒りを助長するのに充分だった。
「てめえの船の船長を売る一味なんざ話にならねェ」
「船長をぶち殺してから、皆殺しだ」
渾身の力を込めて、袋を蹴り飛ばす。袋は吹き飛び、派手な音を立てて壁にぶつかった。キッド一味は沸き立ち、敵の生き残りは引き攣った悲鳴を上げた。船長のみならず船員達も、連日の戦闘を経て、殺気立っていた。
キッドはわざと靴音をたてて袋に歩み寄り、袋の中の船長に語りかける。「なあ、どんな気分だよ。信じてた部下に捨てられるってのはよ」
左腕で革紐で縛られた袋の口を掴んで、引き上げる。
「おれも最近似たような気分を味わったけどな、最低だったぜ」
鈍い音と共に、袋の真ん中に重い拳が叩き込まれた。しばらくサンドバックのように、袋に殴打を加え続ける。一撃喰らわせるごとに、味方から歓声があがった。
「てめえらみたいなのがたかってくるのも、うんざりだ」
ふと、酸味を帯びた臭いが鼻をついた。見ると布袋に薄汚れた染みが広がっている。キッドは笑い、袋を床に投げ出した。
「この程度で吐いてんじゃねえよ、汚ねぇ野郎だな!」
たくさんの嘲り笑う声が、船上に響く。敵船の船員達は、俯いて震えていた。
「下も漏らさねえようにオムツ付けてやろうか?」
「頭はまだ能力つかってすらいねえんだぞ!」
「殺せ!殺っちまえ!!」下卑た歓声も、今は場を血生臭く染めあげるスパイスでしかない。
「次はダーツの的ってのはどうだ?」
キッドが指をく、と動かすと、床に落ちていた短剣が次々と浮き上がり、全て袋に突き刺さった。瞬間、びくりと袋は痙攣した。布地に吸われた血液は、吹き出すことなくじわじわと床を伝って流れていく。
自分は何をしているのだろう、と心の端で思う。こんなことをしてもあの男は帰って来はしない。だが、苛立ちを向ける矛先を求めているのも事実だった。「おれも疲れた。そろそろ楽にしてやるよ」
言って右腕を高々と上げると、刀剣や屑鉄が宙に浮き、吸い寄せられていく。およそ自然の摂理を超越した光景に、場の全員が見入った。呼吸のために上下している袋を強く踏み付ける。靴の裏に硬い感触がした。頭だ、と確信し狙いを定める。
「じゃあな」
一撃が振り下ろされた。骨を砕く音と、床板を破壊する音とが場に居合わせている者達の耳をつんざく。頭を狙うまでもなく袋は完全に潰れ、原型を無くしていた。血や体液でぐずぐずに濡れそぼった袋に、唾を吐きかける。拍手と歓声が巻き起こり、船上は一種狂気的な盛り上がりを見せた。
「次はてめェらだ」
キッドは袋に背を向け、船上を見渡す。返り血を浴びずとも血のように赤い男を見て、生き残り達は身をすくめた。
キッドは一歩踏み出してから、ふと先程の感覚に違和感を覚えた。靴で踏み付けた、頭とおぼしき場所。人間の頭はあれほど硬かっただろうか。まるで、何かを被っているかのような。俯いていた敵が、不意に体を震わせ始めた。恐怖のための震えではない。やがて、堪えきれなくなって声が洩れる。嘲るように。おかしくて仕方が無いというように。
振り返る。
破れた袋の隙間から、渇いた血で茶褐色に汚れた、長い、金色の、
キッドは袋に駆け寄り、一気に布地を引き裂いた。
…
「納得いかない、といった風情だな。殺戮武人」
薄暗い部屋で、紫煙がたなびいている。皮張りの椅子に腰掛けた初老の男は、葉巻を吸いながら悠々と語りかけた。対してキラーは、無様に床に転がっていた。後ろ手で縛られている上、利き足に至っては膝から下で粉々に砕かれているため、身じろぎすらおぼつかない。
キッドと決別したあと、キラーはすぐに後をつけられていることに気づいた。キラーは、密通者の大元を探して根絶やしにするべく動こうとしていた。それが、敢えて何も告げることなく去ったことへのけじめだと考えていたのだ。
そのため、気配に気づいた時はむしろ好都合と解釈した。キッド達に危険が及ぶことなく、全てキラーの内で事が終わる。そのはずだった。
「……見くびっては、いないつもりだった」
「いや?見くびっていただろう。スパイを送り込むような奴は、小細工しかできないと思い込んで」実際、その通りだったのかもしれない。身構えていたにも関わらず、力で押し負けたということがその証拠だ。一方的に痛め付けられた屈辱を思い出し、キラーは歯噛みした。
「自分の強さをひけらかし、無思慮に暴れて自ら懸賞金の額を吊り上げる馬鹿がいるらしいが、その逆も有り得るということだ」
「何が、目的だ」キラーは起死回生を諦めてはいなかった。なんとか多くの情報を得て、キッドに伝える術を探す。無駄死にだけは、避けなければならない。
「あんまりうるさいのは、目障りなんでね」
男はのんびりと煙を楽しみ、緩やかに吐き出した。
「さて、ユースタス・キッドの船は明け方に出航したらしいが……」
銀の葉巻を置き、男は伸びをしながらゆらりと立ち上がった。そして気だるげにキラーの元へ近づくと、砕けた脛に足を乗せ、ゆっくりと体重をかけた。
「ぐああああっ……!!!」
激痛に耐え切れず、キラーは叫び声を上げた。
「今後の戦略構想も兼ねて、お前には色々聞きたいことがある。まあゆっくりしていってくれ」
キラーが拘留されてからの数日、その身にはありとあらゆる手段を用いた尋問が行われた。しかし、キラーは決して口を割らなかった。ひとつでも情報を漏らせば、仲間達を売ることになる。苦痛にも、罵声にも、嘲笑にも、耐えた。その様子を薄笑いを浮かべて眺める船長の男には、吐き気を覚えた。「困るな、お前が喋ってくれないとスムーズに事が運ばない」
仮面も一度は剥ぎ取られたが、何故か船長は被せたままにしておくよう指示し、その日は仮面の上から脳震盪を起こすほど強く殴られた。殺されないのが不思議なくらいの責めだった。
束の間責め苦から解放され、眠りに落ちる時、暗闇の端々にキッド達の姿を見た。
ある日目を覚ますと、やけに外が騒がしかった。海軍と衝突でもしたか、とおぼろげに考えていると、閉じ込められている部屋のドアが開く。
「今、ユースタス・キッドの船と一戦交えている」
船長は、事もなげに告げた。キラーは久し振りに頭がはっきりと覚醒するのを感じた。
(キッド……!)
ある意味、この状況はキッドにとって幸いかもしれない。いくらこの一味が規格外の強さを誇っていても、正面から戦えば勝利はキッドにある。キラーはそれだけキッドの力を信じていた。
「しかし船員はそうでもないが、やはり船長は別格だな。こちらの数も予想以上に削られてしまった。ひどく荒れている風だったよ」
相変わらず、人を小馬鹿にしたような立ち振舞いで、船長の男はキラーに話しかけた。
「どうだお前、こちら側の戦闘員として戦ってみないか?」
ふざけるなと言おうとしたが、喉が痛んでいて声にならなかった。
「まあそれは冗談として、ようやくお前が役に立つ時が来たようだ」
言うや、三下連中が大きな布袋をキラーに被せてきた。身をよじって抵抗するも虚しく、袋の口はきつく縛られ、眼前に暗闇が広がった。
「今から私達は降伏する。船長を袋に詰めて差し出すことでな」
「!!」
「あの荒れようでは、中身も見ずに叩き潰すかもしれないな」キラーはキッド達と決別した日から、自らの生を諦めていた。キッドに降り掛かる危機さえ振り払えれば、それで平和になる。今、キッド達が直接この一味を叩き潰しても同じだ。いずれにせよ、キラーはもうキッド海賊団に戻ることは無い。ならば自分が生きていようが死んでいようが、構わないと思っていた。
だが、それはキッド達の目に触れないところで、という前提の下だ。「やめてくれ……」
「何だ、まだ喋れたのか」
「キッドに、おれを殺させるのは、やめてくれ……!!」男は興醒めしたように嘆息した。
「最期くらい、みっともなく命乞いするもんだと思ったんだがね」
ちっとも主語が自分にならない奴だ、と男は爪先でキラーを軽く小突いた。
「これが私達の攻撃だ。どんな砲弾よりも強く、確実に死に繋がる痛みを与える」
「やめろおおォ!!」船員達が、キラーの入った袋を持ち上げた。キラーは残った力を総動員して暴れたが、そう長く抵抗は続かなかった。キラーは、潰れた喉で叫んだ。
「キッドは、おれがいなくたって、ワンピースを見つけられる!!お前達を、殺して……!!!」
袋が運び出されて行った後、船長の男は葉巻を取り出して、火を点けた。
「最期にいいことを教えてやろう」
「ユースタス・キッドの元に送ったスパイは、一人じゃない。この袋が開かれる時、彼らはあの男の背後で剣を振りかぶっている」
男はふっと煙を吐き出し、ひとりごちた。
「しかしつまらない忠犬だったな」
…
初めてキッドがワンピースを手に入れる、と宣言した時、周りの大人が大笑いしたのを不思議に思った。
あいつにはそれだけの器がある。あれほど熱心に海の話をする奴はいない。腕っぷしも強い。何より、あの赤い瞳より強い輝きを放つものを、知らなかった。
キッドと共に、この広く深い海の高みに上りつめたら、そこにはどんな眺めが広がっているのだろう。幼いおれはそれを見たかった。村で1番高い木に登ってもなお、見果てぬ世界を。
だから、笑った奴らをぶん殴った。キッドも大暴れした。結局大人の腕力には敵わなくて、ほとんど半殺しのような目に遭ったが、後悔は無かった。
路地裏に転がったまま、キッドは動けないおれに話しかけた。あの時の傷の痛みも、おぞましい程にぎらつく夕日の残照も、よく覚えている。
『なぁキラー』
『ついてこいよ、世界の果てまで』
おれはその約束を破った。海賊の掟のみならず、最も破ってはならない大切な友との誓いをふいにした。結局何もかもが裏目に出てしまった。独りでどうにかしようと思ったことが悪かったのか。あの時、本当のことを言えば良かったのだ。そうすれば、危険だけは伝えられた。おれが出て行くことは変わらなかったとしても。
きっとおれ自身、キッドだけじゃない、仲間達を信用できていなかったということだろう。自業自得だ。今や、おれはキッドの隙を誘うだけの存在でしかない。
今あらん限りの声で叫び、暴れれば、キッドはおれに気づいて助けてくれるだろうか。しかし、助かったところで、おれはキッドに会わす顔がない。船長を裏切った船員など、一味には不要だ。部下にも、友にも、戻れない。それに、もはやおれの口からは呻き声しか出てこない。
懐かしい声が聞こえる。袋の中だからはっきりとは聞こえないが、昔から知っている声だから、すぐわかる。
投げ出されたな。殺すのか。キッドは辛かっただろう。最低な気分だっただろう。最後までついて来るはずだったおれに裏切られて。
どうせなら、跡形もなく消してくれ。お前がおれを殺したことなど、知られたくない。そして、最悪の事態を避けて欲しい。汚ならしい袋の存在など、気に掛けたりするな。冷たい。熱い。
もういたいだのくるしいだのはわからない。もうわからない。
でも、なんだか、とてもかなしい。
(願わくば、キッドが海賊王になる時、隣に在りたかった)