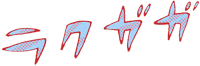只今、縦書きでレンダリング中です。フォントなどダウンロードしています...
遠浅 半世紀近くに渡る航海の始まりはいつだったか。それはもはや遥か遠き日のことだった。見知らぬ島を発見することが珍しくなるほどの年月、海は常に傍らにあった。
今、キラーの眼前には、ごく小さな島がある。猫の額ほどの浜には、変哲もない南国の木々が静かに凪いでいる。恐らく早春の夏島だと思われた。大海賊時代には、多くの猛者達が海へ出た。海面にほんの少し突き出た岩礁ですら、誰かが命名していることだろう。この島にも大層な名が付いているに違いない。
「錨を降ろせ!」
慣れ親しんだ船長の声に、甲板中から船員達の相槌が返る。
全盛期と比較すれば、船は一回り以上小さい。空室の目立つ巨船など虚しいだけだとキッドは言い、馴染んだ船をあっけなく解体して、造り直させた。古参の面子が十数人もいれば、航行するには事足りる大きさだ。船を海岸に固定し、めいめい島に降り立つ。久々に踏みしめる揺るぎない陸地に、長い影が落ちる。もうすぐ日が暮れるだろう。キラーは、とりあえず島を一周するべく歩き出した。立ち寄る島の風土は把握しておきたい。それは、元来集団行動を厭うキラーが孤独を楽しむ口実でもあった。
時折、角の丸くなったガラス片や、船の残骸らしき端材を踏み付ける。その度、さりさりと乾いた音が鳴る。人間の残滓は感じられるが、気配は無い。風の温みだけが、肌にまとわりついていた。
島の輪郭をなぞるように海岸沿いを歩くと、ほんの10分程度で、着岸地点から真反対の砂浜に辿り着いた。水平線が、見知っているより随分と低い位置に引かれている。西日の眩しく乱反射する波飛沫に惑わされて見え辛いが、透明度の高い潮の下、延々と続く砂地が確認できた。遠浅のようだ。目が痛むほど輝く海面とは対照的に、波音はささやかなものだ。しかし、寄せては返す波は、確かに膨大な過去を絶え間なく現在へ還元している。人の経た航海など、 自然の流れの前では微々たるものだ、とふと思う。足元に転がっている白骨のごとき流木も、自分など及びもつかない年月を過ごしてここに在るのだろう。
適当な大きさの流木に腰掛ける。安置しようとした手を、突き出た枝がかすめた。反射的に掌を確認する。傷は付いていない。裂傷のような皺があるだけだ。痩せたような気はしないのに、指の皮は骨に纏わり付き幾重もの溝を刻んでいる。拳を握り込むと、骨と肉が静かに軋んだ。
正直なところ、ここまで命を永らえるとは思いもよらなかった。命を削るように、血潮を絞り出すように、駆けてきたのだ。ゴールテープを切った後も、止まることのできない走者のように。
キッドの船に乗る者は、誰も彼も危うい生き方をしていた。道程で命を落とす者も数え切れないほどいた。それでも誰一人振り返りはしなかった。立ち塞がる者を殺す覚悟は、殺される覚悟と表裏一体だ。その覚悟は、感傷と縁遠いものである。涙を一滴こぼすより、相対する者の心臓に刃を突き立てる方が、弔いに相応しい。そのはずだった。けれど、今は事あるごとに振り返ってしまう。誰も失っていないか。誰も血を流していないか。いつから自分はこれほど弱くなってしまったのだろう。年月と共に積み重なっていく仲間の死を辛いと考えてしまうことこそ、己の老いを自覚する行為にほかならなかった。
いよいよ太陽は海に吸い込まれ始め、不快な程まばゆさを増す。キラーは、直視できず顔を伏せた。目をつむっても、仮面の穴から光は侵食し、白く瞼裏を焼いた。
ふいに、キラーが歩いてきた方角から、砂を分ける気配がした。砂音はゆっくりと近づいてくる。キラーは、特に身じろぎもせずそれを迎えた。「ここは、あの島の浜に似てねェか」
傍らに立ち止まったキッドが言う。あの島、とはキッドとキラーが生まれ育った島のことだ。決して故郷とは口にしない。あれは南の海に浮かぶ、つまらない島だった。何もないので、もっぱらの娯楽は派手に血の噴き出す暴力だった。そんな喧騒に満ちた島も、しかし海辺は静寂が支配していた。太陽に色を奪われた漂流物は、亡骸のように無口だった。
「……少し」
キラーの肩口を、厚い毛皮の袖先がかすめた。しばらく視界の端に暗褐色の革靴がちらついていたが、やがてくぐもった靴音しか聞こえなくなった。だが、遠ざかっていくその音が急に湿り気を帯びたので、キラーは顔を上げた。いつの間にか、キッドの後ろ姿がひどく遠くなっていた。
「どうやってそこまで行った」
革靴がぬるりと潮を纏って光沢を放っている。悪魔の実の能力者は、海に嫌われる。海水に直接触れているわけではないが、多少なり干渉を受けるはずだ。
「この程度の浅さなら、どうってことねえよ」
キッドは振り向きもせず、更に沖の方へ足を運ぶ。しばらく波間を掻き分ける音が騒がしく響いた。水平線へ落下しようとする夕陽が、逆立った頭髪を赤銅色に揺らす。
キラーは無性に不安に駆られた。「キッド!」
「うるせェ野郎だな。お前はおれの親か?」凄むかのような口調だったが、語気は愉快げな色を含んでいた。
「……お前が“キッド”である限りはな」
「ハハ、道理でどこまでもついて来るはずだ」転んでくれるなよ、と声を掛けると、親指で首を切る仕草を返された。名の通り、いつまでも少年のごとき奔放な振る舞いを見せる男だ。キッドを慕う者は、彼の持つそういった自由さに惹かれた。
自由。人はそれを渇望し、規定された枠を叩く。しかし、大方その行為は、自分の望む分だけ枠を広げているに過ぎない。内心は、枠に守られていたいという保身が透けて見える。翻って、リスクを度外視し、何にも囚われないキッドの不遜さは、無法者達にはいたく痛快に映るのだった。それはキラーにとっても同じだった。「キッド?」
急に無口になったキッドに声を掛けたが、微動だにしない。しばし、居心地の悪い間が生じた。ぬるい潮風が、コートを奇妙な生き物のように蠢かせる。しばらくして、キッドは緩慢な動作でキラーの方を振り返った。逆光で表情がよく見えないにも関わらず、間違いなく、口の端が裂ける程の凄絶な笑みを浮かべていることがわかった。
「抜けよ」
ざわざわと肌が粟立つ。辺りに埋もれた闘争の残骸が、砂粒を振り落としながら宙を舞う。それらは瞬く間にキッドの右半身を覆い、いびつな巨腕へと姿を変えた。大味ながらも手の形を模した屑鉄は、挑発するかのように、こちらを小招く動きをしてみせた。
「何を……」
「久し振りに殺り合おうぜ」これまでも、戯れのような手合わせは数えきれないほど行ってきたが、今日は何かが違うように思えた。キッドが一歩距離を詰めてきたので、反射的に腰に提げた曲刀へ手を掛ける。その挙動を認めたキッドは、喉の奥で低く笑った。
例え乗り気でなくても、殺気を滲ませた者と相対する時、キラーが武器を持たないことなどない。金属同士がぶつかり合う音が鋭く響いた。瞬時に背後へ飛び退いて、距離をとる。「つれねェな」
間髪入れず、海面を切り裂くような勢いで、無数の鉄塊がこちらへ放たれた。軌道を見切って避けるが、いくつか目測を見誤り、真っ赤な放物線が空に噴き上がる。
「ハハハハ!手ェ抜いてんじゃねェよ馬鹿野郎!!」
痛みはすぐに闘争心へ置き換えられる。体に染み付いた反射だ。むしろスイッチとも言える。キラーは砂を蹴り、キッドの懐へ入り込もうと目論んだ。キッドは悪魔の実の特性上、遠距離からも攻撃が可能だ。キラーが対抗するには、敏捷性を活かして近接戦に持ち込むしかない。キッドもそのことを重々承知しているため、阻む術は持っている。小さな島の中を、鈍く、鋭く、重く、軽く、衝撃音が交差した。他の船員が聞き付けて止めに来ないのが不思議なほどだ。急所すれすれの斬撃を繰り出すほど、キッドは愉快そうに口の端を歪めた。昔なら、同じように高ぶれただろうか。今は攻撃の一手一手が慎重になっているのが、自分でもよくわかる。なるべく当てないようにとそればかりに神経を尖らせてしまい、まるで高揚感が得られない。
打ち合いのさなか、ふとキッドの顔から笑みが引いた。「何で、お前はまだこの海賊団にいるんだ」
キッドの有り余る衝動を新時代は歓迎したけれども、ぎらぎらとした野望は否が応にも目立った。出る杭を打とうとする者は多い。新星を叩き墜とさんとする力に抗っている間に、ひとつなぎの秘宝がかの麦わら一味によって発見されたと報じられた。
麦わら帽子の海賊が導き出した未来は、世界を鮮やかなものに変えたが、新たな時代は真昼の太陽のように健全なきらめきに満ちていた。居心地が悪い。地獄のような灼熱は耐えられるのに、温かくこちらを包むような空気の中では、呼吸もままならない。「もう何も手に入らねェのに」
何よりも、研ぎ澄まされた牙が磨耗していくのが恐ろしかった。
「……おれは、お前と行くと決めたから」
キッドの表情が一瞬寂しげな子どものように揺れた。しかし、それは本当に刹那のことだった。
「だからてめェはいつまでも半端なんだよ、キラー!!」
選んだ言葉は、暴風雨のごとき猛攻で返された。穴だらけになった砂浜に、次々と赤い滴りが吸い込まれていく。
「お前のそれは、惰性でしかねえ。目的を失った船長の後を追って、何が得られる?何が望める?」
追い討ちをかけるように、鉄の腕が叩きつけられた。わずかにかすっただけで、吹き飛ばされそうな衝撃を受ける。ほんの少し仰け反った隙に、容赦なく連撃を注がれる。舞い上がる砂埃で、視界も満足に確保できない。
「もう駄目だと、一度でも思わなかったか?」
遠のきかけた意識の中、キッドの声だけがやたら明瞭に聞こえた。キラーは、もはや視覚など頼らず声のする方へ駆けた。正面から飛んでくる鉄塊がいくつも身を切ったが、速度を緩めることはしなかった。その勢いを殺さず、水面を蹴る。
そして、決して避けられない間合いへと、飛び込んだ。
「おれは、お前の夢を死なせたくなかった」
噴き出したと思ったのは、夕陽の赤だった。
「志半ばで、お前を……死なせたくなかったんだ」
キラーは独り、かそけく揺れる波間に立ちすくんでいた。夕映えを受けた潮が、血溜まりのように生ぬるく足元を濡らした。
キラーがキッドに代わり船長を務めだして、どれほどの年月が経過しただろうか。皆が慕い、海賊王の器と信じていたユースタス・キッドはもういない。
死とは、いたく簡単なものだった。今まで屠ってきた余多の命と同じく、的確に急所を抉られれば、少し血を流しすぎれば、どんなに強い者でも死ぬのだ。すべてが一瞬で消え失せた。言葉さえ、表情さえ残されはしなかった。
船長亡き後、『キッド海賊団』の旗を掲げることに難色を示した者も少なくなかった。すぐ離反する者もいたが、実質的な副船長であるキラーの判断を待つ者が大半だった。結局キラーは航海を続けることを選んだ。ひとつなぎの秘宝を探すでもない、力を誇示するわけでもない、ただあてどなくさまようだけの旅だ。『キッド海賊団』の名を海に漂わせ続けることで、過去と化した男を、生かしたかったのだ。
その行為が、残された者の慰めに過ぎないと分かっていても。きっとあの男は、それを望まないと分かっていても。水平線が、太陽を飲み込んだ。世界を照らす光が薄れていく。
キラーは、海中に没した太陽を、いつまでも見つめていた。