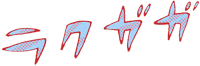只今、縦書きでレンダリング中です。フォントなどダウンロードしています...
太陽に伏す 何が違うのだろう、とキラーは思った。
マストの上で見渡す青も、地上で見上げる青も、色彩に違いはない。
小高い丘の、背の低い熱帯植物が群生する地帯。木陰と言うにはあまりに心もとない空間に腰を下ろし、見上げた空はやはり青い。
見上げずとも空と海と港町は一望できるのだが、人は太陽を仰がずにはいられない。ヒマワリか何かのようだと思う。
時折湿度をまとった青臭い風が吹き抜けて、ああ違うのは色じゃなくて空気かと気づく。ひとりでいると詮無いことばかり考えてしまうものだ。しかしながらその時間は一団に属す身には貴重なもので、孤独を愛する性はこうした無駄で満たされるのだった。
ずっと海の上で箱に詰められていれば、どんな寂しがりだろうと外へ飛び出したくなる。錨を下ろすが早いか街へ駆け出していく船員達の姿に、キラーはひとりになる大義名分を得る。今日からしばらくは次の島へ向かうためのログを溜めなければならない。その間決まっていることといえば、簡単な船のメンテナンスと火薬や食材の補充、最終日に船へ戻ることくらいだ。あとは仲間が、主に船長が乱闘騒ぎを起こすことも計算に入れねばならない。事によっては今見えている風景が消えてなくなるかもしれない。
柔らかい葉の茂る木に背中を預ける。日暮れまでひと眠りしようか、そう考え至った時だった。
草を踏む音、衣擦れの音。誰かが丘を登ってくる。
見知った気配だということは早くに気づいた。
「……迷子か?」
「殴られてェか」いいやと笑いを含んだ声で返せば、キッドは苛立たしげに鼻を鳴らした。至っていつも通りの態度だ。
隣に腰掛けるでもなく、目を合わせるでもなく、丘からの眺めを確かめている。そしてあらかた周縁を見尽くした後太陽を見上げたので、気取られないように仮面の中で笑った。「高いところ好きだな、お前」
「そうかもな」急に揶揄するような口調になったので、煙と何とかはと言い出すのかと思えば、
「きっとここにいると思ったぜ」
と自信に満ちた横顔で宣言された。
「いつも高いところにいるよな。ワンパターンなんだよ」
キラーは彼の船長が自分を探していたことに気づいた。
それは少々の驚きを呼び起こす事実だった。「なにもこんな時まで」
「あ?」
「いや、毎日顔を突き合わせてるのによく飽きないなと思った」ああ、とキッドはつぶやき、キラーはろくでもない言い回しをしてしまったと内心頭を抱えた。
嫌なわけじゃない、と取り繕おうとしたがキッドが先に口を開いた。「キラーがいねェと違和感がある」
何のてらいもなく言うので、どう返したものか測りかねた。
光栄だと言ったらきっと不機嫌になるだろう。感謝、親愛、温かさ。それらは彼の忌避してやまないものだ。「……よさそうな酒場がある。ここから見えた」
勢いをつけて立ち上がる。キッドはこちらを一瞥するでもなく、白熱に照らされる世界を見つめていた。
少し後ろに立ち、改めて景色を一望する。
そうだ、空気だ。空気が違う。キッドがいる世界では、空も海も全ての青が彼にひれ伏す。
誰も彼も当たり前のように太陽を見上げるのだ。